芥川賞を受賞した「むらさきのスカートの女」。
何とも奇妙なタイトルで、どんな話なんだろうと思いAmazon kindleでポチっちゃいました。
短編小説なのでサクッと読めてしまいました。
「芥川賞受賞作品」というキーワードからトレンド作品的な位置づけで読もうと思ったわけですが、そんなことは忘れ、「むらさきのスカートの女」と「わたし」の不思議な世界観にどんどん引きずり込まれていき、終わった後にはモヤモヤとした不気味さを植え付けられました。
終わった後には、こういう終わり方をするのか、他の人のレビューを観てみたい、そんな感覚を持たされました。
ってことで、私なりのレビューを書いていきたいと思います。ここからはネタバレを書いていきます。
まだ読んでいない方はこのレビューを読む前に、Kindle版を購入して読んでからレビューを読んでいただけるといいかなと思います。
表紙の絵について
表紙には、黒の水玉が描かれた白い布から膝下から脚が見えている、なんとも不気味な絵が描かれています。
紫のスカートではなく、人が2人いて布を被っているような絵となっています。
これが示すものは、全てを読んだ方には、ぼんやりと理解することができたと思います。
「わたし」目線での「むらさきのスカートの女」に憧れを頂くものの、「わたし」は「むらさきのスカートの女」に近づこうとする。そして、最後には彼女に近い存在になる。そんなことをこの表紙では物語っているのではないでしょうか。
「わたし」について
序盤は「わたし」の存在が全く見えないにもかかわらず、いつも「むらさきのスカートの女」を定点観測していました。
一般的な小説としての定点観測ではなく、「わたし」が登場人物として明確に存在しているにもかかわらず、物語の30%程度は「そこにいる」という情報しか与えられないという、これが非常に不気味でした。
中盤で、「むらさきのスカートの女」がホテルの清掃業の仕事に就いてからトレーニングを受けるシーンで次のような一文があります。
「私は昨日に引き続き、この日も自己紹介するきっかけを逃していた」
ここで、若干ゾクッとしました。
なぜか?
ここまでは、「わたし」という存在が小説としての定点観測者なのではないか?そう思い始めていた矢先に、改めて「わたし」という存在を突き付けられたからです。
この後も、先輩チーフにいじめられてこなくならないか心配するシーンでは、次のような一文が出てきます。
せっかく採用されたのだからもう少し頑張ってほしい。
せめて、わたしと友達になるまでは。
また、所長と「むらさきのスカートの女」のデートシーンで、所長が顔を隠すために野球帽とサングラスをかけるシーンがあるのですが、ここでも次のような一文が出てきます。
わたしがいつもかけているのとよく似た形だったが、たぶんあちらの方が高級品だ。
これらの文章だけをみると、「わたし」に対する狂気性のようなものを感じると思います。
しかし、こういう一文があるにもかかわらず、ストーカー的な異常性や狂気性を感じられず、あくまでも意図が読めない観測行動を続けており、そこに奇妙さとか不気味さを感じます。
これは読んでもらわないと伝わらないので、この世界観を味わってほしいですね。
異常性と存在意義
誰でも持っている普遍的な「異常性」のようなものを表現しているのではないかと感じました。
というのは、「わたし」は商店街を歩く「むらさきのスカートの女」の何か不足した雰囲気に対して勝手な親近感と魅力を感じ、観測をし始めたのではないかと感じました。
この感覚を中学校に例えて言うなら、大抵のクラスの男子はクラスのマドンナ的存在の美女を好きになるとは思うのですが、一部の男子は「自分でも手が届きそう」「可愛くはないけど、好きなタイプの顔」のような理由で、あまり陽の目を見ないような女子を好きになったりします。
意外とそういう女の子って、早くて高校生で一気に可愛くなったり、遅くても社会人くらいで一気に美人になったりするんですよね。
そして、美人になると、変な男も寄ってきてそこに引っかかってしまったりすると、ダメな方に落ちていく。
当時好きだった女子がダメな方に落ちていった話を聞いて、ショックを受ける。
この物語に出てくる「わたし」はいわゆる”一部の男子”、「むらさきのスカートの女」は”陽の目を見ないような女子”、「所長」は”変な男”。
こんな風に捉えてみると、「わたし」が「むらさきのスカートの女」を気になった理由なんていうのは、大した理由ではないちょっとした何かで、やけに執着してしまうのも気になってしまったから執着している。
先に述べた普遍的「異常性」とは、中学生男子的な「異常性」とも言い換えることができますね。
「むらさきのスカートの女」はホテルで働き始め、周りから認められ美人になる一方で、所長から言い寄られ、選択を誤りダメな方に落ちていく。
そんな風に捉えられるのではないでしょうか。
しかし、同性であるがゆえの冷静な観測に対する、少し説明が不足しています。
ここで追加するもう視点は、「わたし」の存在意義としての「むらさきのスカートの女」という視点。
「わたし」はホテルでもほとんど喋らず居場所や存在意義が無いところに、「わたし」よりも若干上の存在である「むらさきのスカートの女」が現れたことで、「わたし」の存在意義に置き換えた。
自身を「黄色いカーディガンの女」として表現し、所長の転落時に求められていないのにいい加減な診断とアドバイスをしたこと、最後にはベンチに座り、「むらさきのスカートの女」になろうとする姿からも、そこに存在意義を見出し、置き換えようという意思がみられました。
まとめ
以上が私が感じた解釈となります。
解釈が正しいとか、書き手の想いとずれている可能性もありますが、読み終わった時に感じたのこのような感覚です。
Amazonのレビューに読み終わった感覚を的確に表現していていいなと思ったコメントとして、”世にも奇妙な物語を一話見たような感覚”というコメントがありました。
これは個人的にはこのコメントが凄くしっくりきていて、なんなら世にも奇妙な物語で40分くらいで放送して欲しいなと共感しました。
<div data-vc_mylinkbox_id=”885950381″></div>
短編なので1~2時間程度で読み切れますのでぜひ読んでみてください。



 dアニメストア
dアニメストア 
 U-NEXT
U-NEXT 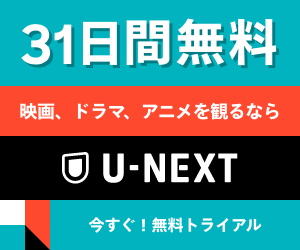
 hulu
hulu 






